提出期限に遅れた原稿の取扱いについて
- 提出期限に遅れた原稿,また未提出の原稿については,12月17日中に提出すれば有効とする。ただし,期限遅れとして1事由の減点を施す。
- 12月17日中に提出されなかった原稿は,(この時点までの減点事由数-編集グループの返却遅れ数)×2を減点してポイントを確定する。なお,減点を2倍するのは,他の有効な原稿との減点機会の公平性を保つためである。
冬期休業期間中の作業について
- 冬期休業中も,これまで通りに作業を継続する。
- ただし,12月27日(月)~1月3日(月)は大学構内に入れないので,作業期間に含めない。
情報をどのように活用するか-引用の方法-
引用の目的
- 自己の考えと他者の考えとを区別する。
- 他者の考えを正確に踏まえて自己の考えを展開していることを示す。
- 他者の考えを正確に踏まえているかどうか,読み手が検討できるような手だてを示す。
- 他者の著作権を尊重する。
著作権とはなにか
著作権の概要
- 著作権に関して詳しく正確に理解するには,社団法人 著作権情報センターのサイトを参考にするとよい。
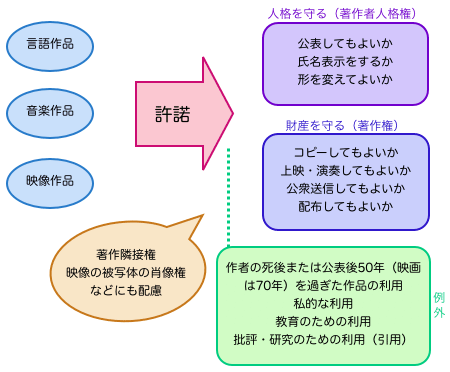 |
著作権を管理している団体
引用の原則
著作権法
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し,その著作の名義の下に公表する広報資料,調査統計資料,報告書その他これらに類する著作物は,説明の材料として新聞紙,雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし,これを禁止する旨の表示がある場合は,この限りでない。
- 引用の必然性があること。
- 自己の文章が主であること。
- 必要最低限の引用であること。
- 引用元(出典)を明記していること。
- 著作権に配慮した引用のガイドラインの例としては,ウィキペディアが参考になる。
自己の文章と引用との関係
引用 |
引用箇所に対する |
自己の考えを |
||||
・引用箇所をどのように理解 ・引用箇所の何を問題にした |
||||||
引用の形式
引用箇所の示し方
- 引用箇所は改変しないように正確に書き写す。
- 引用元の文意を変えないように過不足なく書き写す。
- 引用箇所の分量によって,以下のような方法がある。
引用箇所をカギ括弧で括る
- 地の文の中途で,引用したいときに用いる。
- 引用箇所が短い場合に用いる。
|
||
| ▼ | ||
|
引用箇所で改行する
- 引用箇所が長い場合に用いる。
- 地の文の中途でも用いることができるが,引用箇所が長いので,例のように地の文をいったん終えて引用する方が読みやすい。
引 |
|
||||||
出典の示し方
引用箇所の末尾に示す
- 引用箇所に,出典を示すやり方。
- そのつどすぐに出典を知ることができるので,読み手にはわかりやすいが,引用が多い場合には,うるさい印象がある。
|
||
| ▼ | ||
|
脚注・巻末に示す
- 引用箇所には,注を示し,ページの下部または文章の終わりにまとめて示すやり方。
- 文章中に出典の記述が表われないので,すっきりした印象があるが,読み手が出典を参照したいときには,煩雑になる場合もある。
引 |
実際,インターネットにおける議論では,フレーミング(flaming) と呼ばれる,些細なきっかけから感情にまかせてお互いを罵倒しあうなどの荒れた議論が起こりやすくなると言われている。ウォレスは,匿名性により発言が自己の責任にならないために,社会慣習や制約による抑制が弱まることから,このような攻撃的な行動は,引き起こされる可能性が生じると述べている(7)。こうしたフレーミングを回避する方法として,メッセージの意味内容を解釈するための社会的な手がかりをフェイス・マークのような記号でメッセージに付け加えること(8) や,社会的な手がかりをことばで伝え合うだけの時間的な余裕を持ってコミュニケーションを行うこと(9) などが指摘されているが,一方で,非言語的な手がかりが欠如するからといって,非抑制的な行動が助長されるわけではなく,むしろ敵意のある言語メッセージを用いるかどうかが,攻撃的な行動だと受け取られることに強い影響を及ぼすといった報告もある(10)。 ----------------------------- (7)Wallace, P., 2001( 原著1999), 『インターネットの心理学』, 川浦康至ほか訳,
NTT 出版, p.159 |
出典情報
- 出典の表記の仕方については,分野によって慣例があるので,その分野に関係する本や論文の表記法を参考にするとよい。
- インターネットの情報については,表示の仕方はまだ定着しているとはいえない。また,出版物のように保管されるわけではないので,信頼性の低い情報であるということを踏まえて利用する。
単行本から |
必要な |
著者名,題名,出版社名,初版年月日,引用箇所のページ |
|
表記例 |
中西信行『確かな読みを拓く課題解決学習の新視点』明治図書,2002年11月,pp.95-97 |
||
雑誌論文 |
必要な |
著者名,題名,雑誌名,巻・号,発行年月日 |
|
表記例 |
上田祐二「電子メディアを活用した書くことの学習の基礎論的考察-書くことの双方向性と書くことの双方向的な学習との接点-」『旭川国文』第20号,2006年3月 |
||
単行本に |
必要な |
論文の著者名,論文の題名,単行本の編者,単行本の題名,出版社名,初版年月日,引用箇所のページ |
|
表記例 |
中村功「携帯メールのコミュニケーション内容と若者の孤独恐怖」橋元良明『講座社会言語学2-メディア-』ひつじ書房,2005年5月,p.79 |
||
インターネット |
必要な |
著者,引用記事のタイトル,トップページのタイトル,トップページのURL,参照年月日 |
|
表記例 |
社団法人 著作権情報センター「はじめての著作権講座「著作権って何?」」http://www.cric.or.jp/,2006年11月30日現在閲覧可能 |
引用時の注意点
引用元の主旨を変えない
- 下例で引用した箇所は,引用元の主旨においては,書くことの一面を指摘したものでしかない。このように,引用の形式は適切であっても,引用元の主旨を誤解させるような引用はしないようにする。
|
||
| ▼ | ||
|
引用しないが参考にした場合
- 参考にした文献の表現は用いないが,明らかにそれを参考・参照したことが明らかな場合には,出典を明記するようにする。
- 下例では,ブログの利用状況を自己の文章としてまとめているが,総務省の報告にもとづいているため,出典を明示している。
引 |
しかしながら今日の電子メディアの発展は,こうした書くことの様相を変容させつつある。たとえば総務省は,ここ数年で急速に普及したブログの利用実態について報告している。それによれば2005 年3 月末時点で,国内ブログの利用者は延べ335 万人おり,そのうち月に1 度はブログを更新しているアクティブな利用者でも,約95 万人にものぼるという。利用者は今後も増加の見通しであるが,特に,これまでホームページなどを開設したことのない一般ユーザー,なかでも若年層,女性の開設が急増しているという特徴が示されている(2)。 ----------------------------- (2)総務省, 2005, 「ブログ・SNS の現状分析及び将来予測」, http://www.soumu.go.jp/, 2007年12月13日現在閲覧可能 |
