意見をどのように構成するか
「記事の構想」の取り扱いについて
- まだ提出されていない「記事の構想」については,本日(24日)中に提出された場合には有効とする。
- なお,上記に該当するファイルに対する評定ポイントは,提出された場合には,一事由分(期限遅れ)の減点とする。また,本日中に提出されなかった場合には,0点とする(作業をまったくしなかったという扱い)。
- 未提出のファイルが明日以降に提出された場合,そのファイルを受けつけるかどうかは,編集グループに一任する。ただし,編集グループが受けつけた場合であっても,そのファイルのポイントは0点である(学習効果に配慮した取り扱い)。
- また,アウトラインについて,編集グループから「執筆に取りかかってください」と通知された人は,提出方法をよく理解した上で執筆作業に移って構わない。提出の方法はここ

アウトラインの構成をとらえる
- これまでに作成したアウトラインを,文章構成の面からとらえなおしてみる。
【アウトライン例】
は |
iPodのよさ |
音楽とデータの両方を携帯できる。 |
|
だからいつも持ち歩いている。 |
|||
それによって音楽を聴く時間が増えた。 |
|||
私にとって音楽とは何だろう? |
|||
な |
音楽の効果 |
音楽は心情や雰囲気を演出する効果がある。 |
|
映画のBGM |
|||
酒場で流れる演歌 |
|||
懐メロを聴くと心に浮かぶ思い出 |
|||
携帯電話との |
携帯電話でも着歌・着メロが流行っている。 |
||
その人の個性が,曲の選択に表われている。 |
|||
お |
まとめ |
このようにiPodを携帯する生活は,自分で自分の生活を演出しているのだ。 |
|
でもヘッドフォンをつけて自分だけの世界を楽しむ姿は,少しさみしいかもしれない。 |
|||
- およそ以下のような構成になっているかを点検してみよう。
- 参考【一般的な文章構成のタイプ】
三段構成
- はじめ→なか→おわり
- 問題提起・話題提示→説明・根拠づけ→主張
四段構成
- 起→承→転→結
- 問題提起・話題提示→説明・根拠づけ→視点の転換・反論の検討→主張
意見の論理性を支える要素
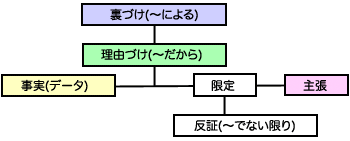 |
||||||||||||
|
||||||||||||
中村敦雄(1993)『日常言語の論理とレトリック』教育出版センターによる |
- これらの要素を踏まえると,【アウトライン例】における各アウトライン項目が,文章全体に対してどのような役割を持つかをつかむことができる。
- たとえば下例の場合,文章を論理的に展開するためには,赤枠の部分が必要であることが分かる。
【例1】
- 理由づけと裏づけが書かれていなければ,事実から何を言いたいのかが曖昧になったり,なぜ3つの事例を挙げているのかが分かりにくい文章になる。
- 裏づけが示せない場合には,主張の強さを弱める(「~だろう」など)必要がある。
|
||
| ▲ | ||
|
||
| ▲ | ||
|
||
| ▲ | ||
|
【例2】
- 「なか」の部分の2つの主張は,結論となる主張に対しては,根拠であることがわかる。
- したがって,根拠1・2から,結論となる主張がどのように導けるのかを説明しなければ,「なか」と「おわり」との論理的な関連性がわかりにくい文章になる。
|
||
|
||
| ▼ | ||
|
||
| ▼ | ||
|
文章の構成と論理の展開
- 以上のように,文章の基本的な構成は,3つの要素からとらえられる。
- だとすれば「起→承→転→結」のような構成において,「視点の転換・反論の検討」といった要素は,何のためにあるか。
- こうした要素の働きは,牧野(2004)が示した以下の構造でとらえることができる。
 |
 |
|
 |
 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
 |
 |
|
 |
 |
|||||
牧野由香里(2004)「論理構築力とメディア活用能力の分析に基づくグループ学習の効果」『日本教育工学会論文誌』28-2 |
|||||||||
論理の系列I:論証の中核
- 「主張」の論理性を支えるためには,「根拠」となる事実と,その事実の信頼性を高める「サポート材料」が必要になる。
- 「主張」と「根拠」とが,仮説としての「主張」を「根拠」となる事実にあてはめて検証する(演繹法),「根拠」として収集した事実から一般化した「主張」を導く(帰納法)といった,論理的な関係にあることが重要である(その関係の説明が「理由づけ」)。
|
|
|
|||
【例】
- 前節【例1】は,理由づけにおいて,「根拠」から帰納法を用いて「主張」を導いていることがわかる。
|
||
| ▲ | ||
|
||
| ▲ | ||
|
論理の系列II:主張の価値づけ
- 「主張」にどういう意義・価値があるのかを支えるために,「主張」がどのような問題に対する「主張」なのかがわかるように「問題となる背景」で,するどく問題提示を行う必要がある。
- また,「結論」において,導き出した「主張」が,提起した問題にとってどのような価値があるのかを説明すると,説得力が出る。
|
|
|
|||
【例】
- iPodを携帯した生活を,書き手がどのような判断をしているのかを,「主張」と関係づけた「結論」として加えることによって,文章の意図が明確になることがわかる。
|
||
| ▼ | ||
|
||
| ▼ | ||
|
論理の系列III:主張の強化
- 「予想される反論」を導出し,それを「論破」することによって,主張の優位性を示す。
|
|
|
|||
【例】
- 元のアウトラインの締めくくりは,自己卑下した言い方でおかしさの効果をもたせたということもできるが,iPodが自分に閉じこもる生活を招くのではないかという「反論」としてとらえることもできる。
- 文章の論理性を高めるという点では,それを「予想される反論」として,それを「論破」する説明を加えることによって,「主張」を強固なものにできることがわかる。
|
||
| ▲ | ||
|
||
| ▲ | ||
|
