その他 (Under construction)HEADLINE
- 講義・実験用補助ファイル
①中学校理科実験Ⅱ
・光学顕微鏡の使用方法
・細胞の観察
・葉緑体の観察,原形質流動と原形質分離
・植物の葉脈の観察(葉脈標本の作製)
・植物の維管束の観察
・植物の花の構造
・水中の微生物の観察
・同化デンプンの検出(エタノール抽出とたたき染め法)
・アミラーゼによるデンプンの加水分解
・質量保存の法則(気体の発生と沈殿)と定比例の法則(銅の酸化)
・酸化銅の還元,銅原子の保存(移り変わり)
・金属間の電位差の測定
・物体の運動(自由落下,斜面を下りる台車の運動)
・光の性質(反射,屈折,凸レンズによってできる像)
・音の性質(音叉,真空鈴,オシロスコープで音を見る)
・回路を流れる電流の強さと電圧の大きさ
・電流が磁界から受ける力(電気ブランコとリニアモーター)
・簡易モーター(クリップモーター)の作成
・大気圧と雲の発生,空気の重さの測定
・火山灰中の造岩鉱物の観察
②小学校理科教育法
小学校の教員になるためには,小学校教諭免許状を取得する必要があるが,小学校は中学校や高等学校とは異なり,国語,算数,理科,社会,音楽,図工,体育,家庭など多くの教科を一人で教えなければならない。そのため,小学校教員志望の学生は,大学で様々な教科指導科目を履修し,これらの教科を広く浅く学ぶことになる。中学校や高等学校教員志望の学生が,一つの教科を専門として深く学んでいくのとは,この点で異なる。
北海道教育大学においても,「小学校理科教育法」の2単位のみが必修で,「初等理科」は教科内容研究科目として選択科目となっており,大学生活4年間のうち,理科の科目は最低2単位(15回の講義+試験)だけで,将来小学校教員として理科の授業を行うことができる。この科目は,100名程度の受講生がいるので,当然,観察や実験などを行うことは不可能であり,残念ながら講義形式を取らざるを得ない。したがって結果として,教員養成大学でありながら,理科を専攻している学生以外は,大学で試験管や顕微鏡を一度も触らずに卒業し,小学校の理科室で理科の実験指導を行っているのが現状であろう。
このことは,そもそも大学の教職課程のカリキュラムで,小学校理科教育法などの教科指導科目を最低2単位履修すれば要件を満たしてしまう,教育職員免許法上の制度に無理があることを意味している。忌々しいことではあるが,最近では,児童・生徒の理科嫌いや理科離れどころか,小学校教員の理科嫌いや理科離れを指摘する理科教育関連の論文も見受けられるようになってきた。小学校教諭免許状を取得するために,小学校教員志望の学生は,全ての教科指導科目を「広く浅く」学習することになるが,これでは小学校教師が理科の指導に自信が持てず,理科嫌いになるのも無理はない。これは免許制度のシステムであり,ここで議論してもどうにもならないことではあるが,理科教育を担当する大学教員が十分に認識しておかねばならない課題であろう。
そういった意味では,小学校理科教育法では理科の学習指導案の書き方や授業設計などの解説も大切ではあろうが,まずは理科という教科の特徴である観察と実験を中心とした内容の理解,そして観察・実験を支える理科の教材・教具について理解させることが何より重要である。
一般に,教科教育法と言うと,学習指導案の書き方を学んだり,板書方法や発問の仕方を検討したり,マイクロティーチングのような模擬授業を学生に行なわせることと思われている節があるが,これは適当ではない。これらはあくまで教育的な技術であって,教科の内容や教材を十分に把握した上で,行うべきものである。こうした技術は,本来,教師が日々の教員生活を行う中で体得すべきであり一朝一夕で身に付くものではない。世の中では即戦力,実践力などという言葉がはやっているが,大学はあくまで体系化された理科学習の理論や内容をじっくりと時間をかけてきちんと学ぶべき場であり,こうした授業技術は,本来教師になってから教育委員会等の教員研修で習得すべきもので,教育委員会の教科担当の指導主事の業務であろう(そもそも教員免許状自体,大学ではなく都道府県が出している)。したがって,大学という場で,短絡的に付け焼刃の授業テクニックを身に付けることだけは避けたい。
一方,公立小学校の教員になるためには,各都道府県が実施する教員採用候補者選考検査(教員採用試験)に合格しなければならない。教員採用試験では,小学校全科として,理科の内容に関する問題も出題される。昨今では,試験において模擬授業を課すところがあり,その中で理科の実験指導について問われることもある。こうしたことから,たとえ小学校の一教科に過ぎない理科であっても,疎かにはできない。
以上のような現状を踏まえると,大学においては,受講人数の制約から観察や実験を行うことが極めて困難な状況ではあるが,2単位という限られた時間の中で,できる限り将来の観察や実験指導に役に立つような講義を展開する必要がある。そこで,学習指導要領の流れに沿って,観察や実験の教材や器具の写真などをふんだんに取り入れ,小学校理科の内容の基礎知識の習得とともに,教員採用試験の学習にもつながるような演習問題も盛り込み,少しでも小学校教員志望の学生諸君の一助になるようにと構成にしたのが本書である。
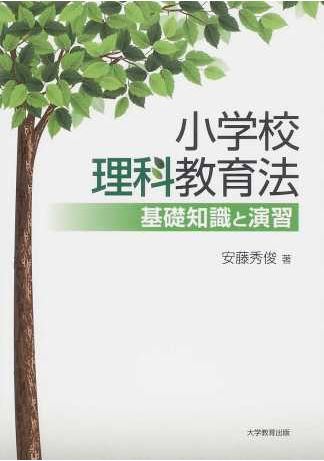
・第3学年の目標および内容
・第4学年の目標および内容
・第5学年の目標および内容
・第6学年の目標および内容
③理科教育演習
・
④高等学校理科教育法Ⅰ
・
⑤理科教育特論Ⅱ
・
・光学顕微鏡の使用方法
・細胞の観察
・葉緑体の観察,原形質流動と原形質分離
・植物の葉脈の観察(葉脈標本の作製)
・植物の維管束の観察
・植物の花の構造
・水中の微生物の観察
・同化デンプンの検出(エタノール抽出とたたき染め法)
・アミラーゼによるデンプンの加水分解
・質量保存の法則(気体の発生と沈殿)と定比例の法則(銅の酸化)
・酸化銅の還元,銅原子の保存(移り変わり)
・金属間の電位差の測定
・物体の運動(自由落下,斜面を下りる台車の運動)
・光の性質(反射,屈折,凸レンズによってできる像)
・音の性質(音叉,真空鈴,オシロスコープで音を見る)
・回路を流れる電流の強さと電圧の大きさ
・電流が磁界から受ける力(電気ブランコとリニアモーター)
・簡易モーター(クリップモーター)の作成
・大気圧と雲の発生,空気の重さの測定
・火山灰中の造岩鉱物の観察
②小学校理科教育法
小学校の教員になるためには,小学校教諭免許状を取得する必要があるが,小学校は中学校や高等学校とは異なり,国語,算数,理科,社会,音楽,図工,体育,家庭など多くの教科を一人で教えなければならない。そのため,小学校教員志望の学生は,大学で様々な教科指導科目を履修し,これらの教科を広く浅く学ぶことになる。中学校や高等学校教員志望の学生が,一つの教科を専門として深く学んでいくのとは,この点で異なる。
北海道教育大学においても,「小学校理科教育法」の2単位のみが必修で,「初等理科」は教科内容研究科目として選択科目となっており,大学生活4年間のうち,理科の科目は最低2単位(15回の講義+試験)だけで,将来小学校教員として理科の授業を行うことができる。この科目は,100名程度の受講生がいるので,当然,観察や実験などを行うことは不可能であり,残念ながら講義形式を取らざるを得ない。したがって結果として,教員養成大学でありながら,理科を専攻している学生以外は,大学で試験管や顕微鏡を一度も触らずに卒業し,小学校の理科室で理科の実験指導を行っているのが現状であろう。
このことは,そもそも大学の教職課程のカリキュラムで,小学校理科教育法などの教科指導科目を最低2単位履修すれば要件を満たしてしまう,教育職員免許法上の制度に無理があることを意味している。忌々しいことではあるが,最近では,児童・生徒の理科嫌いや理科離れどころか,小学校教員の理科嫌いや理科離れを指摘する理科教育関連の論文も見受けられるようになってきた。小学校教諭免許状を取得するために,小学校教員志望の学生は,全ての教科指導科目を「広く浅く」学習することになるが,これでは小学校教師が理科の指導に自信が持てず,理科嫌いになるのも無理はない。これは免許制度のシステムであり,ここで議論してもどうにもならないことではあるが,理科教育を担当する大学教員が十分に認識しておかねばならない課題であろう。
そういった意味では,小学校理科教育法では理科の学習指導案の書き方や授業設計などの解説も大切ではあろうが,まずは理科という教科の特徴である観察と実験を中心とした内容の理解,そして観察・実験を支える理科の教材・教具について理解させることが何より重要である。
一般に,教科教育法と言うと,学習指導案の書き方を学んだり,板書方法や発問の仕方を検討したり,マイクロティーチングのような模擬授業を学生に行なわせることと思われている節があるが,これは適当ではない。これらはあくまで教育的な技術であって,教科の内容や教材を十分に把握した上で,行うべきものである。こうした技術は,本来,教師が日々の教員生活を行う中で体得すべきであり一朝一夕で身に付くものではない。世の中では即戦力,実践力などという言葉がはやっているが,大学はあくまで体系化された理科学習の理論や内容をじっくりと時間をかけてきちんと学ぶべき場であり,こうした授業技術は,本来教師になってから教育委員会等の教員研修で習得すべきもので,教育委員会の教科担当の指導主事の業務であろう(そもそも教員免許状自体,大学ではなく都道府県が出している)。したがって,大学という場で,短絡的に付け焼刃の授業テクニックを身に付けることだけは避けたい。
一方,公立小学校の教員になるためには,各都道府県が実施する教員採用候補者選考検査(教員採用試験)に合格しなければならない。教員採用試験では,小学校全科として,理科の内容に関する問題も出題される。昨今では,試験において模擬授業を課すところがあり,その中で理科の実験指導について問われることもある。こうしたことから,たとえ小学校の一教科に過ぎない理科であっても,疎かにはできない。
以上のような現状を踏まえると,大学においては,受講人数の制約から観察や実験を行うことが極めて困難な状況ではあるが,2単位という限られた時間の中で,できる限り将来の観察や実験指導に役に立つような講義を展開する必要がある。そこで,学習指導要領の流れに沿って,観察や実験の教材や器具の写真などをふんだんに取り入れ,小学校理科の内容の基礎知識の習得とともに,教員採用試験の学習にもつながるような演習問題も盛り込み,少しでも小学校教員志望の学生諸君の一助になるようにと構成にしたのが本書である。
・第3学年の目標および内容
・第4学年の目標および内容
・第5学年の目標および内容
・第6学年の目標および内容
③理科教育演習
・
④高等学校理科教育法Ⅰ
・
⑤理科教育特論Ⅱ
・